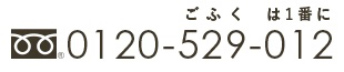2025年03月31日
着物の虫干しはいつやる?自宅で簡単にできる方法と時期
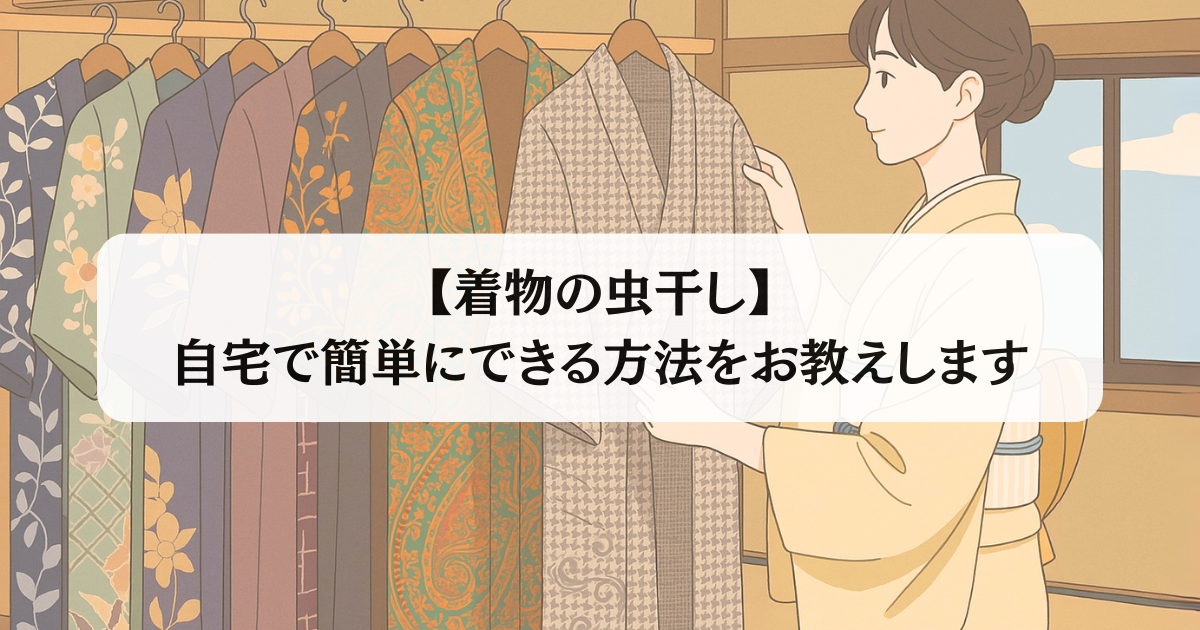
着物は日本の伝統文化の象徴ですが、適切に管理しないとカビや虫害に悩まされることがあります。特に大切なのが「虫干し」です。虫干しをすることで、湿気を飛ばし、着物を長持ちさせることができます。
本記事では、自宅で簡単にできる虫干しの方法や、収納時の注意点について詳しく解説します。忙しい方でも実践しやすいポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。大切な着物を美しく保つために、今日からできるケアを始めましょう!
たんす屋恒例2025年FINAL SALE

たんす屋の展示即売会「2025ファイナルセール」を浅草で開催しました!
リユース着物・帯が最大70%OFF。 12/11(木)〜14(日) 東京都立産業貿易センター台東館7階。
盛況の中終了いたしました。ご来場ありがとうございました。
目次
- 1.はじめに
1-1. 着物の虫干しとは?
1-2. なぜ虫干しが必要なのか?
1-3. 虫干しに適した時期と気候条件 - 2.虫干しをする前の準備
2-1. 必要な道具
2-2. 事前にチェックすべきポイント
2-3. 部屋で虫干しをする場合の注意点 - 3.自宅でできる虫干しの方法
3-1. 屋外での虫干し(ベランダ・庭)
3-2. 室内での虫干し(部屋の中での工夫)
3-3. クローゼットやタンスの中での湿気対策 - 4.虫干し後のお手入れと収納方法
4-1. 防虫剤や乾燥剤の使い方
4-2. 正しい畳み方と収納場所のポイント
4-3. 虫干し後にすべきチェック事項 - 5.まとめ
5-1. 定期的な虫干しの重要性
5-2. 長持ちさせるための工夫
5-3. 忙しくても簡単にできる虫干しの習慣化
1. はじめに
1-1. 着物の虫干しとは?
「虫干し(むしぼし)」とは、着物や和服を湿気や害虫から守るために、風通しのよい場所で陰干しすることを指します。
虫干しの起源は古く、平安時代の宮中行事として記録されていますが、江戸時代に広く年中行事として定着しました。
日本の伝統的な衣類である着物は、絹や木綿といった天然素材が多く、湿気を含みやすいため、定期的な虫干しが必要なのです。
虫干しをすることで、着物にこもった湿気を取り除き、カビやシミの発生を防ぐだけでなく、防虫効果も期待できます。また、長期間収納していた着物の状態をチェックする良い機会にもなります。
1-2. なぜ虫干しが必要なのか?
着物はデリケートな繊維で作られているため、湿気や虫害によってダメージを受けやすい衣類です。虫干しを怠ると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- カビの発生:湿気がこもると、黒カビや白カビが発生し、シミや臭いの原因になります。
- 虫害(衣類害虫):ヒメマルカツオブシムシやイガなどの害虫は、着物の繊維を食べてしまい、穴が開くことも。
- シワや変色:長期間収納していると、折り目が強くついたり、黄ばみが発生することがあります。
虫干しを行うことで、これらの問題を未然に防ぎ、着物を長く美しく保つことができます。

1-3. 虫干しに適した時期と気候条件
虫干しを行うのに適した時期は、一般的に「土用の虫干し(夏)」と「秋の虫干し」の2回です。
- 土用の虫干し(7月下旬~8月上旬)
夏の強い日差しと高温で、湿気を飛ばしやすく、防虫効果も高いですが、直射日光を避ける必要があります。 - 秋の虫干し(10月~11月)
湿度が下がり、涼しくなった頃が最適。カビや虫害のリスクを減らし、冬の長期保管前に行うのがおすすめです。
また、虫干しをする日は、晴天が続いていて湿度が低い日を選びましょう。雨の日や湿度の高い日は逆効果となるため、避けるのがポイントです。

2. 虫干しをする前の準備
2-1. 必要な道具
虫干しをする際には、以下の道具を準備しておくとスムーズに行えます。
- 衣紋掛け(えもんかけ):着物をかけて干すための専用ハンガー。形崩れを防ぐために必須。
- 白い布やシーツ:直射日光やホコリを避けるために、着物の上からかける。
- 手袋(木綿やシルク):素手で触ると皮脂が付着し、シミの原因になるため、手袋を着用。
- 乾いた布:ホコリを軽く払うために使用。
- 防虫剤・乾燥剤:虫干し後の収納時に使うと効果的。
2-2. 事前にチェックすべきポイント
虫干しの前に、以下の点を確認しましょう。
- シミや汚れの有無:虫干しの際に汚れを放置すると、変色やカビの原因になります。気になる汚れは専門のクリーニング店で処理しましょう。
- 虫食いの跡:小さな穴や繊維の傷みがないかチェックしてください。
- カビ臭や湿気の有無:収納場所の環境が悪いと、カビ臭がついていることがあるので要確認です。

2-3. 部屋で虫干しをする場合の注意点
屋外で虫干しが難しい場合、室内で行うことも可能です。その際は以下に注意しましょう。
- 風通しの良い部屋を選ぶ(窓を開けて換気)
- エアコンや除湿機を活用する(湿度を下げる)
- 直射日光は避ける(紫外線で色あせの原因に)
- 床や壁に触れないように干す(ホコリや汚れを防ぐ)
3. 自宅でできる虫干しの方法
3-1. 屋外での虫干し(ベランダ・庭)
晴天で湿度が低い日に、ベランダや庭で虫干しをするのが理想的です。
方法
- 衣紋掛けに着物をかけ、風通しの良い場所に置く。
- 直射日光が当たらないよう、白い布をかける。
- 2~3時間程度、風に当てる。
- 取り込む前に、軽くホコリを払い、異常がないかチェック。
注意点
- 直射日光は避ける(色あせ防止)。
- 風が強い日は避ける(着物が飛ばされる恐れ)。
- 屋外での虫干し後は、30分ほど室内で落ち着かせてから収納する。
3-2. 室内での虫干し(部屋の中での工夫)
雨の日や屋外で干せない場合は、室内で虫干しを行います。
方法
- 風通しの良い部屋で、衣紋掛けに着物をかける。
- 除湿機や扇風機を活用し、湿気がこもらないようにする。
- 2~3時間ほど風を当てた後、ホコリを払う。
注意点
- 空気の流れを作るために、2方向の窓を開ける。
- 壁やカーテンに着物が触れないようにする。
- 暖房器具の近くは避ける(熱で生地が傷む)。
3-3. クローゼットやタンスの中での湿気対策
着物の収納場所にも湿気対策を施すと、虫干しの効果が長持ちします。
おすすめの対策
- すのこを敷く:通気性を確保。
- 除湿剤を入れる:シリカゲルや炭を活用。
- 年に数回、収納場所の換気を行う。
4. 虫干し後のお手入れと収納方法
4-1. 防虫剤や乾燥剤の使い方
- 防虫剤は直接着物に触れないように置く(着物の上に置かず、引き出しの隅に設置)。
- 乾燥剤(シリカゲルなど)を併用すると湿気対策になる。
4-2. 正しい畳み方と収納場所のポイント
- 着物はシワを伸ばし、元の畳み方に戻す。
- 桐のタンスが理想(湿気を調整する効果あり)。
- 密閉しすぎない(適度な換気を心がける)。
4-3. 虫干し後にすべきチェック事項
- シミや虫食いの再確認。
- 防虫剤・乾燥剤の交換時期を確認。
- 収納場所の湿気がこもっていないか確認。

5. まとめ
5-1. 定期的な虫干しの重要性
虫干しは、着物を長く美しく保つために欠かせません。湿気や虫害を防ぎ、カビの発生を抑えるために、年に1~2回は行いましょう。
5-2. 長持ちさせるための工夫
虫干し後の収納環境では、以下の点に注意が必要です:
- 通気性の良い場所を選ぶ
- 湿度が40〜60%の環境を維持する
- 直射日光や高温を避ける
- 風通しの良いクローゼットや収納スペースを使用する
防虫剤や乾燥剤を適切に使用する 着物の保存には、適切な防虫対策と湿度管理が欠かせません:
防虫剤に関して
- 天然の防虫剤(樟脳など)を推奨
- 化学的な防虫剤は直接着物に触れないよう注意
- 6か月ごとに交換することを推奨
乾燥剤の使用:
- シリカゲルなどの乾燥剤を収納スペースに入れる
- 定期的に乾燥剤の交換や再生を行う
- 湿気の多い地域では特に重要

除湿シート タンス敷き きもの番(2シート入り)
★天日干しで繰り返し使えて便利な除湿シート!
たんす・衣装ケースの底に敷く、防カビ・除湿・消臭シートです。
備長炭の成分が水分や匂い、有害物質を吸着!
そしてシリカゲルが湿気を吸収し、大切なお着物をしっかり守ります。きもの都粋ECサイト(広告)
着物を着る機会が少なくても、定期的にチェックする 頻繁に着用しない着物でも、定期的な点検が重要です:
チェックのポイント:
- 3〜6か月に1回は取り出して状態を確認
- カビや虫食いの兆候がないか確認
- 折りたたみ部分を変える(シワ予防)
- 通気を促す
- 和装用のブラシでほこりを払う。または、柔らかい布やブラシを使って軽くたたくようにしてほこりを払います
- デリケートな刺繍などの部分のホコリは丁寧に扱いましょう。決してこすってはいけません。
5-3. 忙しくても簡単にできる虫干しの習慣化
- 天気の良い日に30分だけでも風に当てる。
- 部屋の換気をしながら、室内で軽く陰干しする。
- 収納場所の除湿をこまめに行う。

着物のクリーニングやお手入れは明治44年創業、確かな技の悉皆専門店「こうじ屋」へご用命ください。詳細はこちらから
過去のブログ記事

体型カバーも夢じゃない!リサイクル着物スタイルアップ術
「着物は体型を選ぶ…」なんていって着物を着るのを諦めていませんか?実は、選び方や着こなし次第で、体型カバーも細見えも簡単に叶います。お財布にも環境にも優しい「リサイクル着物」なら、初心者も気軽に挑戦可能!

美しい着物を長く楽しむために!正しいクリーニングとお手入れのコツ
着物は間違った方法で扱うと、シミや黄ばみ、カビの原因になることも。大切な着物を美しく保つためのポイントを詳しくご紹介します。

【完全解説】八代目尾上菊五郎襲名へ!歴史・意味・影響を徹底分析
たんす屋を始め、「まるやま・京彩グループ各店舗」ではお得なコラボ企画をご案内中です。詳しくは各店舗まで!
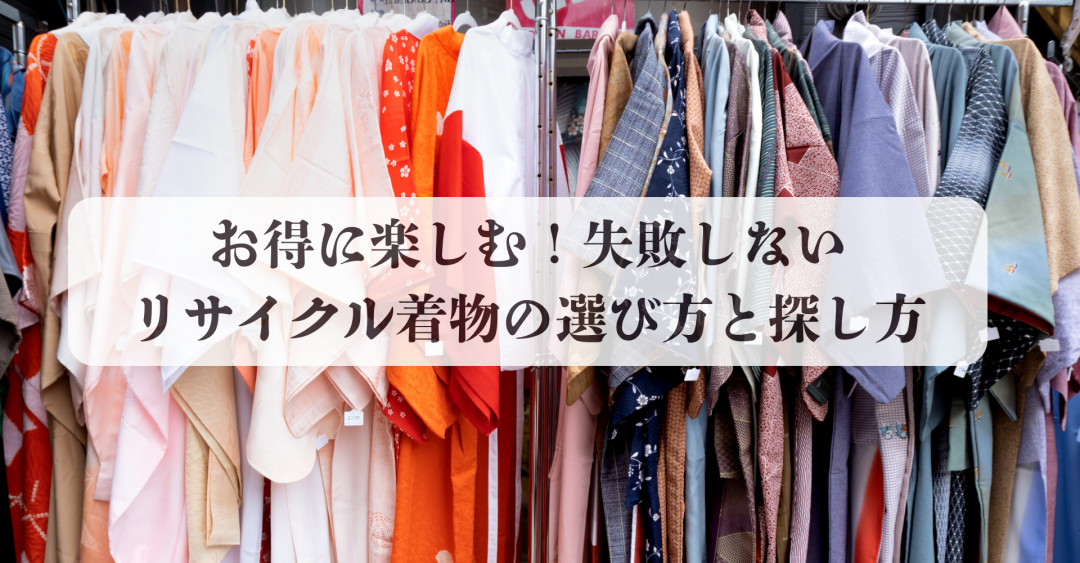
リサイクル着物の賢い選び方・探し方
「着物をもっと気軽に楽しみたい」「お得に素敵な一枚を手に入れたい」。そんな方におすすめのリサイクル着物 (リユース着物)の探し方、選び方をお伝えします。

もう悩まない!着物初心者のための着付け・購入・お手入れ完全ガイド
着物初心者が抱えがちな不安や不満そして悩みをスッキリ解消する方法を紹介しています。