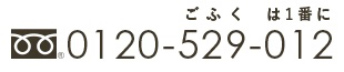2025年03月24日
美しい着物を長く楽しむために!正しいクリーニングとお手入れのコツ

着物は、日本の伝統美が詰まった特別な衣服です。でも、「お手入れが難しそう…」「クリーニングはどうすればいいの?」と悩んでいませんか?
間違った方法で扱うと、シミや黄ばみ、カビの原因になることも。本記事では、自宅でできる基本のお手入れから、プロのクリーニング活用法、保管時の注意点まで徹底解説!
大切な着物を美しく保つためのポイントを詳しくご紹介します。適切なケアで、あなたの着物を末永く楽しみましょう!
たんす屋恒例2025年FINAL SALE

たんす屋の展示即売会「2025ファイナルセール」を浅草で開催しました!
リユース着物・帯が最大70%OFF。 12/11(木)〜14(日) 東京都立産業貿易センター台東館7階。
盛況の中終了いたしました。ご来場ありがとうございました。
目次
1. はじめ
1-1. 着物のお手入れの重要性
1-2. 間違ったクリーニング方法によるリスク
2. 着物の基本的なお手入れ方法
2-1. 着用後のお手入れ(ブラッシング・陰干し)
2-2. 汚れがついた場合の応急処置
2-3. 長期保管前のチェックポイント
3. 着物のクリーニング方法
3-1. 自宅でできる簡単な手入れ
3-2. 専門クリーニング(丸洗い・シミ抜き・洗い張り)
3-3. クリーニングに出す際の注意点
4. 保管方法とカビ・虫食い対策
4-1. 正しい畳み方と収納のコツ
4-2. 湿気対策(防湿剤・除湿器の活用)
4-3. 防虫対策(防虫剤の選び方と使い方)
5. トラブル別の対処法
5-1. シミ・黄ばみが発生したときの対処
5-2. においが気になるときの対策
5-3. 色あせや生地の傷みを防ぐ方法
6. まとめ
6-1. 着物を長持ちさせるためのポイント再確認
6-2. 日頃のケアの重要性
1. はじめに
1-1. 着物のお手入れの重要性
着物は、日本の伝統文化を象徴する衣服であり、美しい柄や織りが施された高価なものが多いですよね。そのため、適切にお手入れしなければ、汚れやシミが残ったり、生地が傷んだりしてしまいます。
特に、着物の生地には 絹(シルク) が多く使われています。絹は湿気や摩擦に弱い性質があります。
また、木綿やウールの着物もあり、それぞれ適したお手入れ方法が異なります。大切な着物を長く美しい状態で保つためには、正しいケアが不可欠です。
日頃からの簡単な手入れを習慣にすることで、以下のメリットがあります。
- シミや汚れの定着を防げる(早めの対処でクリーニングの回数を減らせる)
- カビや虫食いを防ぎ、長期間の保存が可能になる
- 次に着るときに気持ちよく着用できる
着物は一度汚れてしまうと、普通の衣類のように簡単に洗えません。日々のお手入れを怠ると、専門業者に高額なクリーニングを依頼することになったり、最悪の場合、着物自体がダメになってしまうこともあります。
そのため、着物を着た後の簡単なお手入れや、適切な保管方法を身につけることが大切です。
1-2. 間違ったクリーニング方法によるリスク
着物をきれいに保とうとするあまり、間違ったクリーニング方法を実践してしまうと、生地を傷めたり、逆に汚れを広げたりすることがあります。特に、以下のような行為は避けるべきです。
1. 自宅で無理に水洗いする
着物の多くは 絹 や ウール でできており、水に濡れると縮んだり、色落ちしたりすることがあります。家庭用の洗濯機や手洗いで洗おうとすると、生地が変形し、元に戻らなくなることもありますので、避けてください。
一方で、ポリエステル製の着物は、家庭での洗濯が可能な素材としてとても人気があります。水に強く、シワになりにくいため、洗濯機の手洗いモードや手洗いで簡単にケアできます。
洗う際は色落ちを防ぐため中性洗剤を使用し、形を整えて陰干しするとよいでしょう。普段使いの着物として、手軽に楽しむことができます。
また、麻の着物も水洗いが可能で、特に夏物の着物として涼しげな風合いが魅力です。これらの素材は、専門店でのクリーニングを必要とする絹や高級素材と比べて、気軽に着ることができる点が特徴です。

2. シミをこすり落とそうとする
食べこぼしや泥はねなどの汚れを見つけたとき、ついゴシゴシとこすってしまうことがあります。しかし、着物の生地はデリケートなので、こすると摩擦によって生地が傷んだり、汚れが広がったりする可能性があります。シミがついた場合は、適切な応急処置を行い、できるだけ早く専門店で相談するのがベストです。(2-2. 汚れがついた場合の応急処置を参照してください)
3. 直射日光に当てて乾かす
湿気対策のために干すことは重要ですが、直射日光に長時間当てると、紫外線の影響で 色あせ や 生地の劣化 が進んでしまいます。干す際は 風通しの良い日陰 を選びましょう。
4. 化学薬品を使用する
家庭用の漂白剤やシミ抜き剤を使うと、着物の染料が落ちたり、繊維が傷んだりすることがあります。
特に絹はデリケートな素材のため、市販のクリーナーを使う際は注意が必要です。
本章のまとめ
着物は、一般的な洋服とは異なり、特別なケアが必要です。間違ったお手入れをすると、生地を傷めたり、シミが取れなくなったりするリスクがあります。そのため、日々の適切なケアを心がけることが、長持ちの秘訣となります。
次の章では、着物の基本的なお手入れ方法について詳しく解説していきます。
2. 着物の基本的なお手入れ方法
着物を美しい状態で長く保つためには、日常的なお手入れが欠かせません。特に、着用後のケアや汚れがついたときの適切な対処法を知っておくことが大切です。ここでは、基本的なお手入れ方法について詳しく解説します。
2-1. 着用後のお手入れ(ブラッシング・陰干し)
1. 着た後はすぐに汚れやシワをチェックする
着物を脱いだら、すぐに汚れやシワの有無を確認しましょう。食べこぼしや泥はね、ファンデーションの付着など、細かい汚れを見逃さないようにしてください。
特に、袖口・衿・裾は汚れがつきやすい部分なので、入念にチェックしましょう。
2. 軽くブラッシングしてホコリを落とす
ブラッシングは、目に見えない埃や花粉を除去し、繊維に汚れが蓄積するのを防ぎます。繊維の流れを整えて毛玉を予防し、生地の光沢や風合いを長持ちさせる効果もあります。
日々のブラッシングでクリーニング頻度を減らせるため、着物の傷みを軽減できます。さらに、カビや虫食い、嫌な臭いも予防でき、着物を長く美しく保つための大切なケアと言えるでしょう。
特に外出時に砂ぼこりや花粉が付着しやすいため、洋服用の柔らかい ブラシ(馬毛や山羊毛のものがおすすめ)を使い、優しく着物の表面を軽く撫でるようにブラッシングしてホコリを払いましょう。
3. 風通しの良い場所で陰干しする
着物を着た後は、 湿気や汗を飛ばすために陰干し をしましょう。直射日光の当たらない風通しの良い場所で、 1~2時間 ハンガーにかけて干します。
このとき、着物専用の「着物ハンガー」を使うと、形を崩さずに干せます。
☑ ポイント
- 乾燥のムラが生じないように、エアコンの風が直接当たる場所は避けてください
- 陰干し後は、シワが気になる部分を軽く手で伸ばす
2-2. 汚れがついた場合の応急処置
着物に汚れがついてしまった場合、 すぐに適切な処置をすることが重要 です。時間が経つとシミが定着してしまい、落としにくくなります。
1. 食べこぼし(油・醤油・ソースなど)
- 乾いた 白い布(ティッシュやハンカチでも可)で、汚れを押さえるようにして吸い取る
- こすらず、トントンと軽く叩く
- ベンジンを布に少量つけ、シミの外側から内側に向かって軽く叩く
ベンジンは扱いを誤ると危険なため、使用には十分な注意してください。また、シミの種類によってはベンジンでは落とせないものもあります。迷ったら専門家に相談してください。
☑ 注意点
- シルクの着物は水で拭くと輪ジミになるため、水を使わない
- すぐに専門のクリーニング店に相談する
2. 泥はねやホコリ汚れ
- 乾いた状態で、洋服用ブラシ で優しく払う
- 乾いた布で軽くたたき、汚れを落とす
☑ 注意点
- 水で拭くと泥が広がることがあるため、水拭きは避ける
3. ファンデーションや口紅の汚れ
- セロハンテープ を使って、優しくペタペタと汚れを取る
- それでも取れない場合は、少量のベンジンを布に含ませ、軽く叩いて落とす
☑ 注意点
- ゴシゴシこすると、色落ちや生地を傷める原因になる
2-3. 長期保管前のチェックポイント
着物を長期間収納する前に、以下のチェックを行いましょう。
1. 収納前に陰干しをする
保管前に必ず陰干しし、湿気を飛ばします。特に、 梅雨や夏場は湿気がこもりやすいため、風通しの良い場所で1日干すのがおすすめ です。
2. 汚れを完全に落としておく
目に見えない 汗じみ や 皮脂汚れ が残ったまま収納すると、 時間が経って黄ばみやカビの原因 になります。特に長期間収納する場合は、一度専門クリーニングに出しておくと安心です。
3. たとう紙に包む
着物を収納するときは、専用の「たとう紙」に包むと、湿気やホコリを防ぐことができます。(詳細は4-1. 正しい畳み方と収納のコツをご覧ください)
本章のまとめ
- 着用後はすぐにブラッシング&陰干しをする
- 汚れがついた場合は、こすらず応急処置を行う
- 長期保管前には汚れを落とし、湿気対策をする
日頃のこまめなケアが、着物を長持ちさせる秘訣です。次の章では、「着物のクリーニング方法」について詳しく解説します。

3. 着物のクリーニング方法
着物は繊細な素材で作られているため、一般的な衣類のように頻繁に洗うことはできません。しかし、適切な方法でクリーニングを行えば、美しい状態を長く保つことができます。ここでは、自宅でできる手入れ方法や、専門クリーニングについて詳しく解説します。
3-1. 自宅でできる簡単な手入れ
着物は基本的に家庭で洗うことは難しい ですが、ちょっとした汚れや臭いを軽減するために、自宅でできるお手入れ方法もあります。
1. 汗をかいたときの対処
- 汗は 目に見えなくても繊維に染み込んでいる ため、放置すると黄ばみやカビの原因になります。
- 汗をかいた部分(襟や脇など)を 乾いた布で軽く押さえる ようにして、湿気を取る。
- 陰干しをして、風を通して乾燥さます。
☑ ポイント
- こすらず、押さえるように拭く(摩擦によるダメージを防ぐため)
- 毎回の着用後に行うことで、汗じみを防げる
2. 軽いシミ汚れの対処
- ベンジンを布に少量つけ、シミの外側から内側に向かって軽くたたく。
- シミ抜き後は、陰干しをしてしっかり乾かす。
☑ 注意点
- 生地の種類によっては、色落ちのリスクがある ため、目立たない部分でテストする。
- 落ちないシミは無理せず 専門店に相談しましょう。
3. においを取る方法
- 着物にタバコや食べ物のにおいがついた場合は、風通しの良い場所で陰干し をするのが一番です。
- ひどいにおいが気になる場合は、浴室に ぬるま湯を張り、その蒸気で湿気を含ませてから陰干し すると、においが取れやすくなります。
☑ ポイント
- 直接アイロンを当てるのはNG(生地が傷む原因になる)
- 消臭スプレーは使用しない(シミの原因になることがある)
3-2. 専門クリーニング(丸洗い・シミ抜き・洗い張り)
着物は高価な衣服なので、専門のクリーニング店に依頼することが基本 です。着物のクリーニングには、丸洗い、シミ抜き、洗い張りなど様々な方法がありますが、それぞれに特徴と費用が異なります。
クリーニング店を選ぶ際には、これらの情報を事前に確認し、信頼できるお店を選ぶことが重要です。
1. 丸洗い(ドライクリーニング)
- 全体的な汚れやにおいを落とすための方法です。
- 溶剤を使って油汚れや皮脂を落とし、汗じみや臭いを軽減します。
☑ 適したタイミング
- 年に1回程度(頻繁にクリーニングに出すと生地が傷むため)
- 汗を多くかいた夏や、長期間収納する前
2. シミ抜き(部分洗い)
- 着物についた 食べこぼし・泥はね・化粧品の汚れなどをピンポイントで落とす 方法。
- できるだけ 早めに シミ抜きを依頼すると、落としやすい。
☑ 注意点
- 放置すると 黄ばみの原因 になるため、汚れに気づいたらすぐに相談しましょう。
3. 洗い張り(生地を解いて洗う方法)
- 着物を一度解き、反物の状態に戻してから洗う方法。
- 古い着物や、大切な着物のメンテナンスに適している。
☑ 適したタイミング
- 生地がごわついてきたとき
- 長期間保管していた着物をリフレッシュしたいとき

着物のクリーニングやお手入れは明治44年創業、確かな技の悉皆専門店「こうじ屋」へご用命ください。詳細はこちらから
3-3. クリーニングに出す際の注意点
着物を専門店にクリーニングに出す際には、いくつかのポイントがあります。
1. 信頼できる専門店を選ぶ
- 着物はデリケートなため、 着物専門のクリーニング店に依頼することが大切。
- 安価な一般クリーニング店では、適切な処理ができない場合がある。
☑ チェックポイント
- 着物専門の知識を持つスタッフがいるか?
- 過去の口コミや評判を確認する。
2. 事前に汚れやシミの状態を伝える
- どこに汚れがあるのか を伝えることで、的確な処理をしてもらえます。
- 特に汗じみは目に見えないことがあるので、「汗をかいた」「長期間保管していた」などの情報を伝えるとよいでしょう。
3. 仕上がり後の確認をする
- クリーニング後に シミが残っていないか、仕上がりを確認 する。
- 保管する前に、シワがついていないかチェック する。
本章のまとめ
- 軽い汚れやにおいは、自宅で簡単なケアをする
- シミや全体的な汚れは、専門クリーニングに依頼する
- クリーニングに出す際は、信頼できるお店を選び、汚れの状態を伝える
適切なクリーニングを行うことで、着物を長く美しく保つことができます。次の章では、「着物の保管方法とカビ・虫食い対策」について詳しく解説します。
4. 保管方法とカビ・虫食い対策
着物を長持ちさせるためには、正しい方法で保管することが重要です。間違った収納方法では、湿気や虫食いによるダメージ を受けてしまうこともあります。ここでは、着物を安全に保管するためのポイントを詳しく解説します。
4-1. 正しい畳み方と収納のコツ
着物は 適切な畳み方 をすることで、シワや型崩れを防ぐことができます。収納の際には、以下のポイントを押さえましょう。
(着物の適切なたたみ方についてはこちらの記事をご覧ください:リサイクル着物の賢い選び方・探し方)
1. たとう紙に包んで収納する
「たとう紙(和紙でできた着物用の包み紙)」を使うことで、湿気やホコリから着物を守ることができます。
☑ ポイント
- たとう紙は 1年に1回交換 する(湿気やカビの発生を防ぐため)。
- 防虫剤を使う場合は、直接着物に触れないように する。
2. 着物専用の収納ケースを使う
- 桐のタンスは湿気を吸収しやすく、着物の保管に最適です。
- 近年では収納スペースの問題などから、他の素材の収納ケースを使う人も増えています。プラスチック製の収納ケースは湿気がこもりやすいため、防湿剤を一緒に入れる と良いでしょう。
3. 重ねる順番に注意する
- 一番下に丈夫な素材(ウール・木綿)、一番上にデリケートな素材(絹・訪問着)を置く と、生地の傷みを防げる。
☑ 注意点
- 着物を詰め込みすぎると、シワや型崩れの原因 になるので、余裕を持たせて収納する。

着物の収納には桐たんす、桐チェスト、桐衣装ケースがお勧めです
ご用命はまるやま・京彩グループの都粋オフィシャルサイトへ<広告>
4-2. 湿気対策(防湿剤・除湿器の活用)
湿気は着物の カビや変色の原因 となるため、しっかりと対策をしましょう。
1. 収納場所は風通しの良い場所を選ぶ
- クローゼットや押し入れに収納する場合は、こまめに換気 を行い、湿気を溜めないようにする。
- 梅雨の時期は特に湿気がこもりやすいため、扉を開けて空気を入れ替える ことが大切。
2. 除湿剤や乾燥剤を活用する
- 「炭(備長炭や竹炭)」は湿気を吸収し、着物を守る効果がある。
- 「シリカゲル(乾燥剤)」を収納ケースに入れておくと、湿気を吸収しやすい。
☑ ポイント
- 除湿剤は 定期的に交換 する(目安:3~6ヶ月に1回)。
- 新聞紙をたとう紙の間に挟む ことで、余分な湿気を吸収できます。
4-3. 防虫対策(防虫剤の選び方と使い方)
虫食いは、着物の大敵です。特に ウールやシルク の着物は虫に狙われやすいため、しっかりと防虫対策をしましょう。
1. 防虫剤の種類と選び方
防虫剤には ナフタリン・樟脳(しょうのう)・ピレスロイド系 などの種類があります。
| 防虫剤の種類 | 特徴 | 注意点 |
| ナフタリン | 防虫効果が強い | 他の防虫剤と混ぜると化学反応を起こすことがある |
| 樟脳(しょうのう) | 自然由来で安心 | 香りが強いため、使用量に注意 |
| ピレスロイド系 | 無臭で使いやすい | 直接着物に触れないようにする |
☑ ポイント
- 防虫剤は たとう紙の上に置く(直接触れるとシミの原因になる)。
- 複数の種類の防虫剤を混ぜて使用しない(化学反応で着物を傷める可能性がある)。
2. 防虫効果を高めるコツ
- 定期的に収納場所を開けて空気を入れ替える。
- 防虫剤は年に1回交換する(効果が薄れるため)。
☑ 注意点
- 「防虫剤の香りが着物に残るのが気になる…」という場合は、着る前に数時間陰干し をすると、臭いが和らぐ。
本章のまとめ
- 着物は「たとう紙」に包んで収納する
- 湿気対策として、除湿剤や炭を活用する
- 虫食いを防ぐため、防虫剤は適切に使用する
適切な収納と防湿・防虫対策を行うことで、大切な着物を長く美しい状態で保つことができます。次の章では、「トラブル別の対処法」について詳しく解説します。
5. トラブル別の対処法
どんなに気をつけていても、着物には シミ・黄ばみ・におい・色あせ などのトラブルが発生することがあります。しかし、適切な対処を行えば、多くの場合は修復が可能です。ここでは、トラブルごとの対処法を詳しく解説します。
5-1. シミ・黄ばみが発生したときの対処
着物のシミや黄ばみは、時間が経つほど落ちにくくなります。できるだけ早めに適切な対処を行いましょう。
1. シミがついた直後の応急処置
シミの種類によって、適切な対処法が異なります。
| シミの種類 | 対処法 | 注意点 |
| 醤油・お茶などの水溶性のシミ | 乾いた布やティッシュで軽く押さえて吸い取る | こすらない(汚れが広がる) |
| ファンデーション・口紅などの油性のシミ | セロハンテープで軽く押さえて油分を取る | 取れない場合はベンジンを使用 |
| 汗じみ・皮脂汚れ | 乾いた布で押さえて湿気を取る | 放置すると黄ばみの原因になる |
☑ ポイント
- 水を使わず、乾いた布やティッシュで吸い取る
- 広げずに、汚れの中心から外側に向かって処置
2. 黄ばみが発生した場合の対処
黄ばみは、汗や皮脂の汚れが時間とともに酸化して発生します。
対処法:
- 軽い黄ばみ → 専門店の「汗抜きクリーニング」を利用する
- ひどい黄ばみ → 「洗い張り(生地を解いて洗う方法)」を検討する
☑ 注意点
- 自分で漂白剤を使うのはNG(生地を傷める原因になる)
- 着る前に気づいたら、専門店に早めに相談する
5-2. においが気になるときの対策
着物に 汗・タバコ・カビのにおい がついてしまった場合は、正しい方法で除去しましょう。
1. 軽いにおいの場合(汗・食べ物のにおいなど)
- 風通しの良い日陰で 半日~1日ほど陰干し する。
- 湿気を含ませた後に乾燥させると、においが取れやすい(浴室の蒸気を活用するのもおすすめ)。
☑ ポイント
- 直射日光は避ける(色あせの原因になる)
- 消臭スプレーは使用しない(シミや変色のリスクがある)
2. しつこいにおい(カビ・長期保管後のにおい)
- 専用のカビ取りクリーニング を利用する(一般的なドライクリーニングではカビ臭は取れない)。
- 収納ケースに 炭や脱臭剤(竹炭・シリカゲル) を入れて、においを軽減する。
☑ 注意点
- においが気になっても、無理に洗わず、専門店に相談しましょう
- 収納時に湿気対策を徹底することで、カビの発生を防げる
5-3. 色あせや生地の傷みを防ぐ方法
着物の色あせや生地の傷みは、保管方法や着用時の扱い方によって防ぐことができます。
1. 色あせを防ぐ方法
- 直射日光を避ける(陰干しを徹底する)。
- 保管時に たとう紙に包む(光による色あせを防ぐ)。
☑ 注意点
- 紫外線は シルクの色を変色させる ため、絶対に窓際などに放置しないこと
2. 生地の傷みを防ぐ方法
- 汗をかいた後は、早めに陰干しする(湿気を取ることで繊維を守る)。
- 着物の折り目を定期的に変える(長期間同じ状態で保管すると、折り目が傷みやすい)。
☑ ポイント
- 着物を長期間保管するときは、1年に1回はたとう紙を交換し、状態を確認する
- 着用後は、シワを伸ばして保管する
本章のまとめ
- シミ・黄ばみは、早めに専門店に相談する
- におい対策には陰干しと脱臭剤を活用する
- 色あせや生地の傷みを防ぐには、紫外線対策と適切な収納を行う
トラブルが発生しても、正しい方法で対処すれば、着物を美しく保つことができます。次の章では、「まとめ」として着物のお手入れのポイントを総括します。
6. まとめ
着物は、適切なお手入れと保管をすることで、何十年も美しい状態を保つことができます。ここでは、これまでの内容を振り返り、着物を長持ちさせるための重要なポイントを再確認します。
6-1. 着物を長持ちさせるためのポイント再確認
1. 着用後のお手入れを忘れずに
- 軽くブラッシング をしてホコリを落とす。
- 風通しの良い場所で陰干し をして湿気を飛ばす。
- 汚れやシミがないかをチェック し、早めに対処する。
2. 汚れたら適切に対処する
- 汚れは こすらず、すぐに乾いた布で押さえる。
- 油汚れやファンデーションは ベンジンを使って軽く叩く。
- 落ちない汚れは、すぐに専門クリーニングへ 依頼する。
3. 適切な保管方法で長期間守る
- たとう紙に包んで収納 し、湿気やホコリを防ぐ。
- 防湿剤・防虫剤を活用 して、カビや虫食い対策をする。
- 収納場所を定期的に換気 し、湿気をためないようにする。
4. 専門クリーニングを上手に活用する
- 年に1回程度の丸洗い で、全体の汚れを落とす。
- 黄ばみやシミが発生したら、早めにシミ抜きを依頼 する。
- 長期間保管していた着物は、洗い張りでリフレッシュ する。
6-2. 日頃のケアの重要性
着物を美しく保つためには、日頃のこまめなケアが一番大切 です。
✅ 日常のチェックを習慣にする
- 着用後は 汚れやシワを確認する。
- 保管中も 定期的に状態をチェックする(虫食いやカビが発生していないか)。
✅ 「しまいっぱなし」にしない
- 1年に1回は 虫干し をして、湿気を飛ばす。
- たまに着物を出して 畳み直す と、生地のシワや変形を防げる。
✅ トラブルが起きても慌てずに対処
- シミや汚れがついたら、こすらず応急処置 をする。
- クリーニングや仕立て直しで修復可能な場合が多い ので、専門店に相談する。

着物のクリーニングやお手入れは明治44年創業、確かな技の悉皆専門店「こうじ屋」へご用命ください。詳細はこちらから
おわりに
着物は、手入れさえしっかりすれば、何世代にもわたって受け継ぐことができる貴重な衣服です。日頃のケアを大切にしながら、美しい着物を長く楽しみましょう。
最新ブログ記事

体型カバーも夢じゃない!リサイクル着物スタイルアップ術
「着物は体型を選ぶ…」なんていって着物を着るのを諦めていませんか?実は、選び方や着こなし次第で、体型カバーも細見えも簡単に叶います。お財布にも環境にも優しい「リサイクル着物」なら、初心者も気軽に挑戦可能!
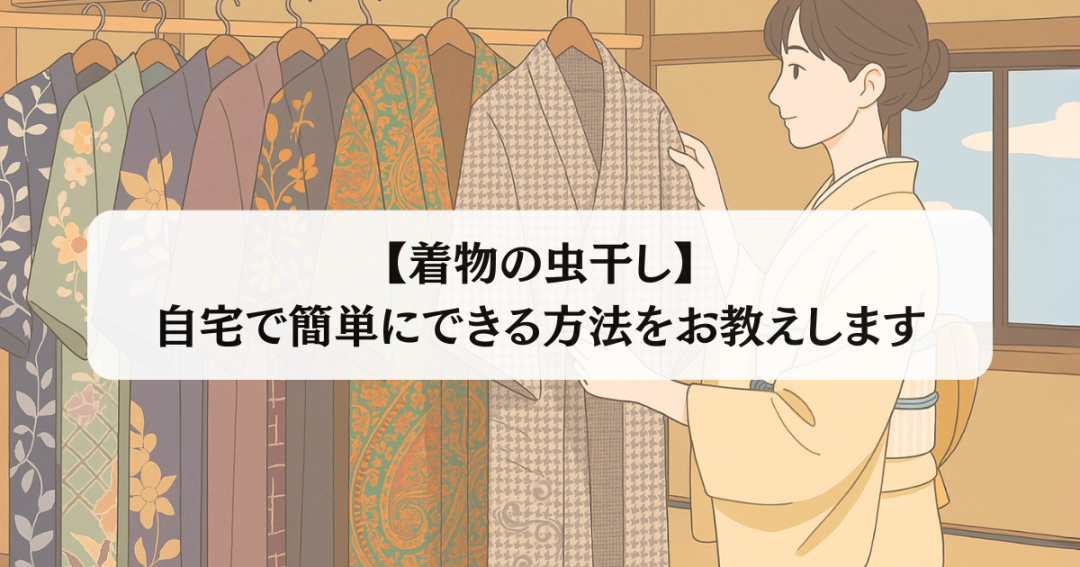
【着物の虫干し】自宅で簡単にできる方法をお教えします
着物は日本の伝統文化の象徴ですが、適切に管理しないとカビや虫害に悩まされることがあります。特に大切なのが「虫干し」です。虫干しをすることで、湿気を飛ばし、着物を長持ちさせることができます。

【完全解説】八代目尾上菊五郎襲名へ!歴史・意味・影響を徹底分析
たんす屋を始め、「まるやま・京彩グループ各店舗」ではお得なコラボ企画をご案内中です。詳しくは各店舗まで!
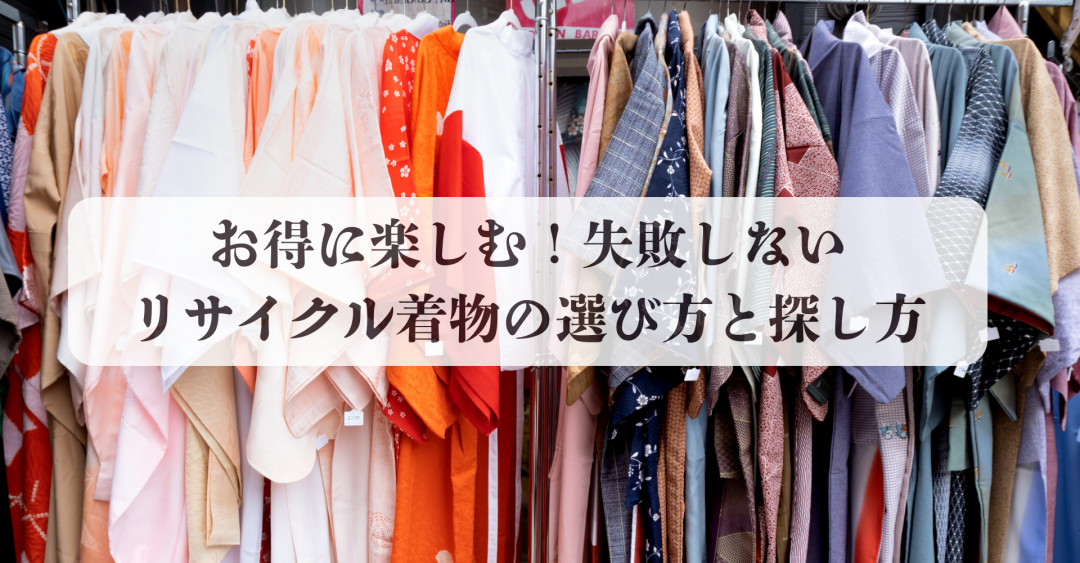
リサイクル着物の賢い選び方・探し方
「着物をもっと気軽に楽しみたい」「お得に素敵な一枚を手に入れたい」。そんな方におすすめのリサイクル着物 (リユース着物)の探し方、選び方をお伝えします。

もう悩まない!着物初心者のための着付け・購入・お手入れ完全ガイド
着物初心者が抱えがちな不安や不満そして悩みをスッキリ解消する方法を紹介しています。